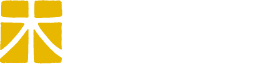変えるべきこと、
変わらないこと。

大工の重要な仕事の一つに「墨付け」があります。墨付けとは、木材を加工するために目印を入れること。
木材のクセを見抜き、経年変化を見越し、どこにどの材を使うかを決める作業でもあり、大工は自分の頭の中の立体図にあわせて、印を入れていきます。
こうした伝統的な技術を受け継ぎながらも、木又工務店では自分たちが検証し、優れていると感じた最新技術も積極的に導入。変えるべきこと、変わらないことを柔軟に選び、細部までていねいに仕上げていきます。
大工の技術と道具

墨付け(墨壺・墨さし)
墨付けとは、木材を柱や梁などに加工する前に、どの木材を家のどこに使うか墨糸・墨差しで印をつけていく技術です。
印をつけるには、木のクセや特性を踏まえた上で経年変化を考慮して判断する必要があるため、非常に難易度の高い技術です。
墨付けができるようになると、大工として一人前とみなされます。
-


きざみ
(鋸 のこぎり)墨付けされた木材を、鋸(のこぎり)で継ぎ手や仕口に加工する技術です。細かい作業のため、手作業で行います。
-


はつり
(手斧 ちょうな)鋸で製材された材木の表面を手斧(ちょうな)と呼ばれる斧で削り、さらに形を整えていく技術です。
-


きざみ
(ノミ)鋸と同様に、墨付けされた木材をノミを使って手作業で細かく加工する技術です。
-


しあげ
(槍鉋 やりがんな)材木を削った後、さらに表面を美しく加工する技術です。槍鉋で削った面は味わい深い凹凸が生まれます。
-


しあげ
(鉋 かんな)槍鉋と同じく、材木を削り表面を加工する技術です。鉋を使うとより平滑な仕上がりになります。